令和6年の10月はまさに秋がなかった。報道などでも結構話題になっていたが
前日まで殆ど真夏日、翌日は15、6度。これでは秋を感じるどころか自律神経が
失調し体調を崩される人が続出するのは無理もない。このような異常気象が続いて
しまうと「秋の夜長」などと言う情緒あふれる言葉も死語になって行く感さえある。
実はこの「春夏冬」は天候気象を表現する言葉ではなく、判じ物と言う日本古来
からの洒落であり「秋」がない。要するに「あきない」となる。これに「二升五合」
を加えて「商いますます(1升をひと升と呼んでいた)繁盛(はんじょう、1升の
半分)」とのオチなのだ。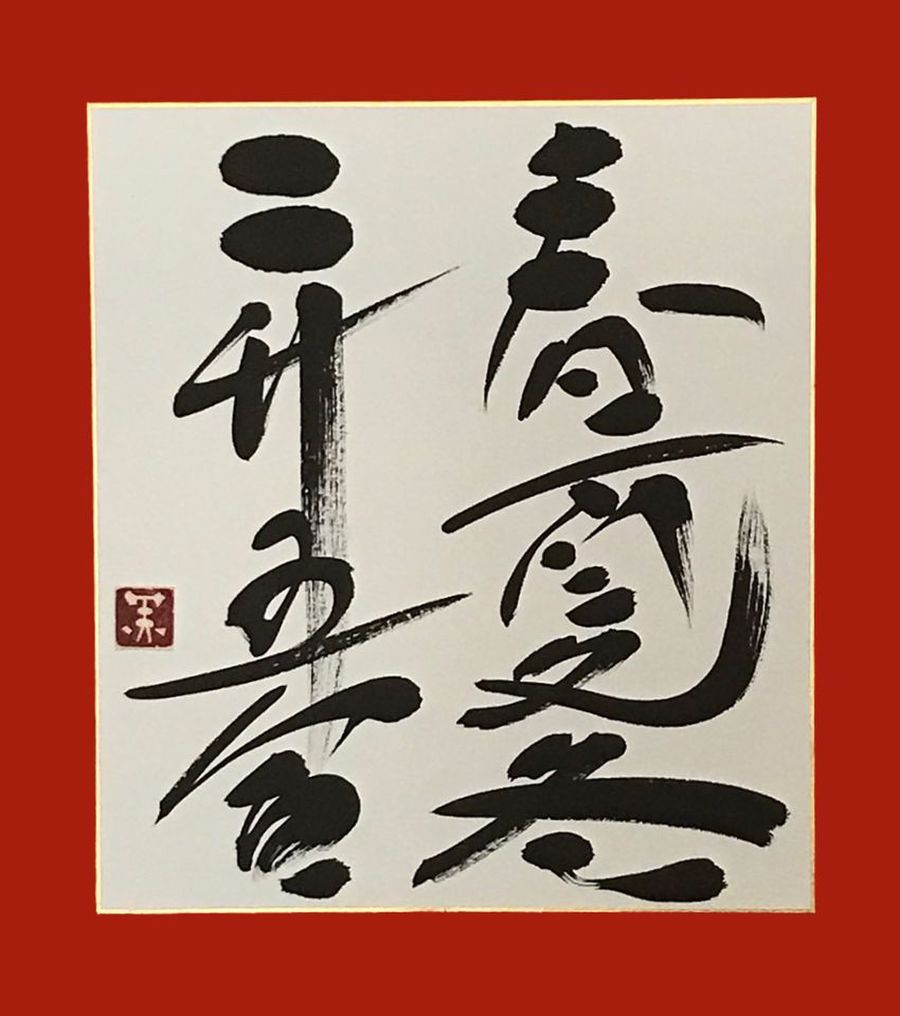
これを少しばかり捻って「春夏冬中」。これは「しゅんかとうちゅう」ではなく、
「あきない中」。英語では「Open」とでもなるのだろうが、其処にこんな洒落っ気
の存在は聞いたことがない。まぁ日本語しか喋れない私が他の言語を評することは
烏滸がましさの極みであることには違いない。
日本人はこんな洒落っ気と言うか言葉遊びが大好きであり、隠語や符丁のような
言葉も星の数ほど存在する。私もこんな大阪商人の洒落言葉が大好きで一時はこれ
ばかりが頭の中を支配していた時期もあった。ほんの一例ではあるが・・・
「うどん屋の釜」(湯ぅだけ⇨言うだけ)
「アイツはホンマにうどん屋の釜やんけ。」
「石屋の宿替え」(重い石をたくさん運ぶ⇨重い重い⇨思い思い⇨まとまりがない)
「あの会社は石屋の宿替えやがな。」
「無地の羽織」(本来あるはずの羽織に紋がない⇨紋なし⇨文無し)
アイツから飲みに誘われたけどカネがない。「俺今文無しなんだよ。」では野暮で
みっともない。これを「ワイ今無地の羽織やねん。」と言い換えると少しは相手も
やんわりと感じるのではないか。
「アイツは春の夕暮れ」やからなぁ。(春の夕暮れは暮れそうでなかなか暮れない。
⇨くれそうでくれん⇨ケチ。これではうかうか飲みに行けない。
このように「言うだけで行動力がない」、(組織に対して)「まとまりがない」
とか「ケチ」など誹謗中傷となるような言葉は(以前に述べた言霊のこともあり)
直接口に出すことは憚られることだった。しかし昨今ではSNS等でも(顔も姿も
見えず、名前も知らないが故に)相手に配慮することも無く、ダイレクトな言葉が
飛び交い、挙句には訴訟に至ることなども多い。世の中がギスギスしてきた証左で
あろうとは思うことは多いのだが、たとえ敵であっても相手を尊重し、敬意を払う
ことも出来なくなった(私を含め)多くの日本人は何時からこんな浅ましい民族に
なってしまったのだろう。
(6.10.23記)
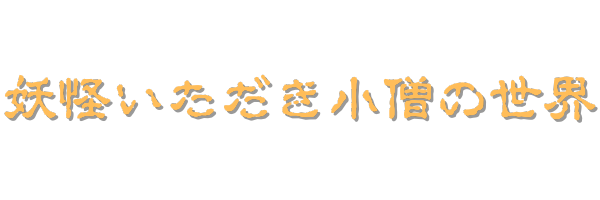

コメント